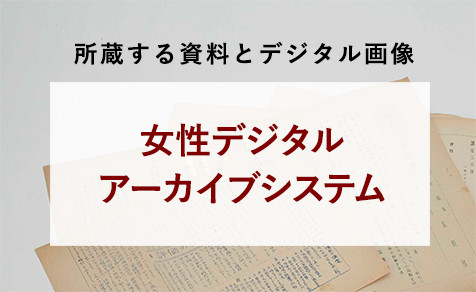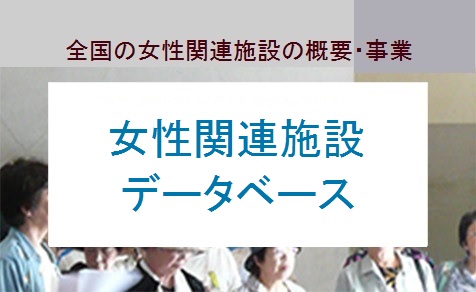国際連携
- (NWEC・ヌエック)男女共同参画の推進機関
- 国際連携
- 国際協力機構との連携
- 令和7年度バングラデシュ国別研修「ジェンダーに基づく暴力撤廃に向けた能力強化」
国際協力機構との連携
- 実施報告
-
令和7年度バングラデシュ国別研修「ジェンダーに基づく暴力撤廃に向けた能力強化」
開催期間:令和7年7月7日(月)~令和7年7月25日(金)
国立女性教育会館は、国際協力機構(JICA)からの委託を受け、令和7年7月7日から25日まで、バングラデシュ国別研修「ジェンダーに基づく暴力(GBV)撤廃に向けた能力強化」を開催しました。この研修には、バングラデシュの南東部に位置するコックスバザール県を中心としたGBV対策に携わる行政官とNGO職員の合計14名が参加しました。
本研修は、3週間にわたる来日プログラムとして実施されました。研修の目的は、国際的な基準である被害者中心アプローチに基づく支援や、日本とバングラデシュのGBV対策、および民間の取組と多機関連携について理解を深めることです。講義や訪問を通じて、多様な機関に所属する参加者同士で活発な意見交換や情報共有が行われました。プログラムの終盤では、参加者が帰国後に実施する研修計画を作成し、最終報告会で発表しました。
第1週:7月7日(月)~11日(金)
プログラムのオリエンテーション後、参加者は各自のGBV対策における役割を発表し、互いの機関について理解を深めました。大谷美紀子弁護士による基調講演では、GBV撤廃に向けた国際法の枠組みや、女子差別撤廃条約の歴史的経緯について学びました。
日本政府の取組として、内閣府からは男女共同参画施策について、文部科学省からは「生命(いのち)の安全教育」についての講義がありました。バングラデシュは、政治や教育分野のクオータ制やポジティブアクションにより、世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ・ランキングが日本より高い一方、児童婚が深刻な課題であることも共有されました。「生命(いのち)の安全教育」が、性暴力の被害者、加害者、傍観者にならないための多面的な啓発であることに関心が寄せられました。
また、JICAのGBV撤廃に向けた取り組み方針や、パキスタン・ケニアの案件における事例紹介を通じ、パイロット活動の形成・実施のプロセスや重要な視点についても学びました。
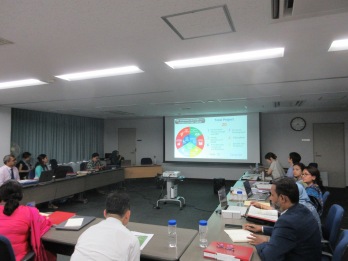 発表の様子
発表の様子
 基調講演講師との記念写真
基調講演講師との記念写真
 グループ討議の結果を説明する参加者
グループ討議の結果を説明する参加者

コラボレーション実践研究所の山中京子所長による講義とワークでは、行政、司法、医療、NGOといった多岐にわたる関係機関の連携の意義を確認しました。
地方自治体と協働するNPO法人女性ネットSaya-Sayaでは、暴力の背景にある偏見や思い込みを可視化するワークを行い、非暴力社会の基盤となる考え方を話し合いました。
 連携についての模擬事例に基づくワーク
連携についての模擬事例に基づくワーク
 暴力の根底にある偏見について考えるワーク
暴力の根底にある偏見について考えるワーク
第2週:7月14日(月)~18日(金)
NPO法人女性・人権支援センターステップの栗原加代美理事長による、DV加害者プログラムについて対話形式の講義後、バングラデシュでも加害者を対象にしたアンガーマネジメントが必要であるという意見が出ました。
一般社団法人日本フォレンジックヒューマンケアセンターの長江美代子代表理事の性暴力支援ワンストップセンターについての講義では、トラウマ・インフォームド・ケアについて学び、記憶力や判断力の低下といったトラウマを抱える被害者への支援理解が深まりました。
 加害者プログラムについての講義
加害者プログラムについての講義
 グループ討議に取り組む参加者
グループ討議に取り組む参加者
男女共同参画センター横浜「フォーラム」を訪問し、情報ライブラリや相談センター、様々な講座を通じて、女性のエンパワーメントやスキルアップ、さまざまな行政の支援に繋がる窓口としてセンターが機能していることを学びました。当日は、JICA横浜センターの海外移住資料館も訪問し、日本の移住の歴史に触れました。
 男女共同参画センター横浜「フォーラム」での講義
男女共同参画センター横浜「フォーラム」での講義
 日本の移住の歴史に触れた海外移住資料館の見学
日本の移住の歴史に触れた海外移住資料館の見学
大東文化大学の齋藤百合子特任教授による講義では、日本在住の外国人コミュニティが直面している課題や多文化共生社会をすすめる上での、インターネットやSNS上のリスクが話し合われました。
GBV被害者の支援現場である自治体の取組について学ぶため、東京都中野区役所を訪問しました。酒井直人区長のご挨拶に続き、ユニバーサルデザイン推進担当課長から、区の男女共同参画の取組や公立学校での啓発事業について伺いました。続いて、中野区を拠点とするNPO法人女性のスペース結からは、DV被害者女性の居住支援や子ども食堂の取組を通じて、地域で安心して暮らせる環境づくりがGBV被害者支援に不可欠であることを学びました。
 中野区長表敬訪問
中野区長表敬訪問
 女性のスペース結の子ども食堂への訪問
女性のスペース結の子ども食堂への訪問
法務総合研究所の山下拓郎国際協力部教官の講義では、子どもの被害者への二次被害やトラウマから保護するための司法面接について学びました。
NPO法人レスキュー・ハブの代表による講義の後は、夜のアウトリーチ支援の現場を見学しました。
第3週:7月22日(火)~25(金)
NPO法人チャイルド・ファンド・ジャパンからは、バングラデシュでも問題となっているオンライン性的搾取(CSAM)の法規制強化、生成AIによる被害の急増などについて情報提供を受けました。
一般社団法人社会的包摂サポートセンターの訪問では、全国規模のホットラインやSNS相談による伴走支援について話を聞きました。多言語による支援への関心が高く、参加者からは、母語での相談サービスが相談者を安心させるだろうという感想が聞かれました。
 チャイルド・ファンド・ジャパンによる講義
チャイルド・ファンド・ジャパンによる講義
 社会的包摂サポートセンターへの訪問
社会的包摂サポートセンターへの訪問
SOGIESCの概念についての講義では、支援の枠組みを策定する際にマイノリティが直面する課題を把握し、支援が必要なすべての人々を取りこぼさないことの重要性が強調されました。
最終週には、参加者が帰国後に協力して実施する研修案をまとめ、オンライン発表会で報告しました。閉講式では、修了証書が一人ひとりに授与され、3週間に及ぶ来日研修が締めくくられました。
 オンライン発表会
オンライン発表会
 閉講式における参加者代表のスピーチ
閉講式における参加者代表のスピーチ
研修にご協力いただいた関係省庁、中野区役所、男女共同参画センター横浜「フォーラム」、民間団体、研究者の講師の皆さまに、この場をお借りして感謝申し上げます。
国際連携
- NWECの国際連携事業について
- 国際研修
- 2019年度アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成30年度アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成29年度 アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成28年度 アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成27年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成26年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成25年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成24年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成23年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成22年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー
- 平成21年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー
- 平成20年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー
- 平成19年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー
- NWECグローバルセミナー
- 令和7年度NWECグローバルセミナー テクノロジーを悪用したジェンダーに基づく暴力(TFGBV)への対応 ~見えない危害を根絶するためのアプローチ~
- 令和6年度NWECグローバルセミナー ジェンダー平等とケア
- 令和5年度NWECグローバルセミナー 誰一人取り残さないジェンダー主流化に向けたメカニズム
- 令和4年度NWECグローバルセミナー デジタル技術はジェンダー平等を推進するか?
- 令和3年度 NWECグローバルセミナー ジェンダーに基づく暴力との闘い ーコロナ危機からの”より良い復興”に向けて
- 令和2年度 NWECグローバルセミナー 新型肺炎とジェンダー
- 2019年度 NWECグローバルセミナー ジェンダーとメディア
- 平成30年度 NWECグローバルセミナー 女性の活躍促進に向けた取組み アイスランドの経験から学ぶ
- 平成29年度 NWECグローバルセミナー 女性の活躍促進に向けた取組み ドイツの経験から考える
- 平成28年度 NWECグローバルセミナー 女性の活躍促進に向けた取組み~ヨーロッパの経験から考える~
- 平成27年度 NWEC国際シンポジウム ジェンダー平等と女性の経済的エンパワーメント
- 平成26年度 NWEC国際シンポジウム~ダイバーシティ推進と女性のリーダーシップ
- 平成25年度 NWEC国際シンポジウム 男性にとっての男女共同参画
- 平成24年度 NWEC国際シンポジウム 女性に対する暴力のない社会の構築に向けて
- 平成23年度 NWEC国際シンポジウム 災害復興とジェンダー
- 平成22年度 女性のエンパワーメント国際フォーラム 女性リーダーの育成に果たす教育の役割
- 平成21年度 女性のエンパワーメント国際フォーラム 女性に対する暴力の撲滅に向けて
- 平成20年度 女性のエンパワーメント国際フォーラム〜人身取引問題の解決に向けたグローバル・パートナーシップ〜
- 30周年記念国際シンポジウム
- 国際協力機構との連携
- 令和7年度課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」
- 令和7年度課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」
- 令和7年度バングラデシュ国別研修「ジェンダーに基づく暴力撤廃に向けた能力強化」
- 令和6年度課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」
- 令和6年度課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」
- 令和5年度課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 令和5年度課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」
- 令和4年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 令和4年度 課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」
- 令和3年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 令和2年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 2019年度課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 平成30年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 平成29年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 平成28年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 中米・カリブ地域における女性の経済的自立に関する基礎情報収集調査ワークショップセミナー (エルサルバドル・ドミニカ共和国)
- 平成27年度 JICA課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進セミナー」
- 中南米地域広域ジェンダーセミナー
- 平成26年度 JICA課題別研修「アジア諸国における人身取引対策協力促進セミナー」
- 平成25年度 JICA地域別研修「アジア諸国における人身取引対策協力促進セミナー」
- 平成25年度 JICA「カンボジア ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ2 2013年度国別研修」研修生一行が来館
- 平成24年度 JICA地域別研修「アジア諸国における人身取引対策協力促進セミナー」
- 平成23年度 JICA国別研修タイ「人身取引被害者支援に関する日タイ合同ワークショップ」
- 平成22年度 女性の教育推進セミナーⅡ
- 平成22年度 JICA国別研修タイ「人身取引に関する日タイ合同ワークショップ」
- 平成21年度 女性の教育推進セミナーⅡ
- 平成21年度 JICA国別研修タイ「人身取引に関する日タイ合同ワークショップ」
- 平成21年度 国別研修ナイジェリア
- 平成20年度 女性の教育推進セミナーⅡ
- 平成19年度 国別研修(カンボジア)
- 平成18年度 女性の教育推進セミナーⅡ
- 平成18年度 国別研修(アフガニスタン)
- 国際会議・国際交流
- 「第44回嵐山祭り」に出展します
- 「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)に出展しました(報告)
- 「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)に出展します
- 清泉インターナショナルスクールの小学生とオンライン会議
- マンスフィールド・フェロー来館
- 第69回 国連女性の地位委員会報告
- JICA課題別研修「中米統合機構加盟国向け ビジネスを通じた女性のエンパワメント」研修員来館
- サスティエ・ムブンバ・ナミビア共和国大統領夫人来館
- べアテ・シロタ・ゴードンアーカイブ資料受贈記念研究会開催
- 第68回 国連女性の地位委員会報告
- 韓国女性政策研究院(KWDI)との懇談会
- フィンランド女性協会連合(NYTKIS)事務局長カッコラ氏の上川外務大臣表敬訪問
- フィンランド女性協会連合(NYTKIS)事務局長カッコラ氏の来日プログラム
- 第67回 国連女性の地位委員会報告
- 韓国女性政策研究院(KWDI)とのウェビナー開催報告(オンライン)
- 第66回 国連女性の地位委員会(ハイブリッド開催)報告
- 筑波大学「Appropriate Technology(適正技術教育)」プログラム大学院留学生への情報提供(オンライン開催)
- 第65回 国連女性の地位委員会(オンライン開催)報告
- 第65回 国連女性の地位委員会(オンライン開催)
- 講演会「ミルズカレッジのベアテ・シロタ・ゴードンアーカイブ」
- 2nd Asian Gender Trainers’ Network Program 参加報告
- 第64回 国連女性の地位委員会
- 国立台湾大学 Wang教授来館
- 【NPO法人日本女性技術者科学者ネットワーク 男女共同参画学協会連絡会】第9回日中韓女性科学技術指導者フォーラム
- 韓国女性政策研究院(KWDI)研究員来館
- ベトナム国防省来館
- 先進7カ国の女性リーダーに関する世論調査「レイキャビク・リーダーシップ指数」報告会
- 広西チワン族自治区婦女連合会代表団 来館
- 第63回 国連女性の地位委員会参加報告
- 韓国両性平等教育振興院2018年度国際シンポジウム「学校におけるジェンダー平等教育」
- 中華全国婦女連合会 来館
- 第7回ジェンダー統計グローバルフォーラム
- 第62回国連女性の地位委員会参加報告
- UN Women石川雅恵所長来館
- 蔚山(ウルサン)施設公団 女性人力開発センター来館
- ドイツにおけるジェンダー平等
- 韓国両性平等教育振興院「女性のリーダーシップをエンパワーする:影響とイノベーションの拡大」
- 第61回 国連女性の地位委員会出席
- バティス女性センター(Batis Center for Women)来館
- 国際会議「持続的開発のためのジェンダーに配慮した教育」
- 第60回 国連婦人の地位委員会出席
- 「第7回アジア太平洋地域における開発とジェンダーフォーラム」が開催されました
- 平成27年度 職員研修(男女共同参画)
- ベトナム女性連合の女性開発センター視察団来館
- ベトナム国防省代表団来館
- 第59回 国連婦人の地位委員会
- フランス女性研究者来館
- カンボジア王国で学術調査を実施
- 韓国女性政策研究院(KWDI)前女性親和政策戦略委員長ヤン・エギョン氏来館
- 中華人民共和国で学術調査を実施
- 第58回 国連婦人の地位委員会出席
- お茶の水女子大学/カナダ女性研究者来館
- カンボジア王国で予備調査を実施
- フィリピン共和国で学術調査を実施
- カンボジア王国法務省次官が来館
- 韓国両性平等教育振興院(KIGEPE)等訪問
- 第57回 国連女性の地位委員会出席
- インドから災害管理専門家が来館
- 韓国女性政策研究院(KWDI)副院長一行来館
- 平成25年度 JICA「カンボジア ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ2 2013年度国別研修」研修生一行が来館
- ストラスブール大学 シュスター博士来館
- 第5回 人の移住に関する世界社会フォーラム
- 韓国女性政策研究院(KWDI)訪問
- カンボジア王国女性省関係者来館
- ベトナム財務省・女性の地位向上委員会代表団来館
- ハワイ大学表敬訪問
- 米国・日本・韓国・フィリピンの女性リーダーの学際的知的交流プログラム
- ハワイ東西センター バーカー博士来館
- 第56回 国連女性の地位委員会出席
- ベトナム情報通信省職員来館
- 韓国両性平等教育振興院来館
- 2011 Asia Women Eco-Science Forum(日中韓科学技術指導者フォーラム)
- カンボジア王国女性省大臣来日
- 女性研究者のエンパワーメントと新領域創成に向けた日米シンポジウム
- カンボジア王国女性省と交流と協力に関する協定を締結
- カンボジア王国女性省主催国際会議
- 中国延辺大学女性研究センターと交流・協力協定を締結
- フィリピン大学機構と学術協力に関する協定を締結
- 韓国女性政策研究院(KWDI)25周年記念式典に出席
- 国立女性教育会館30周年記念国際シンポジウムを実施
- 国立女性教育会館・韓国両性平等教育振興院協定締結記念シンポジウム
- 韓国両性平等教育振興院の国際シンポジウムに出席
- 韓国女性開発院と研究交流・協力協定を締結
- 韓国両性平等教育振興院と交流・協力協定を締結
- (NWEC・ヌエック)男女共同参画の推進機関
- 国際連携
- 国際協力機構との連携
- 令和7年度バングラデシュ国別研修「ジェンダーに基づく暴力撤廃に向けた能力強化」