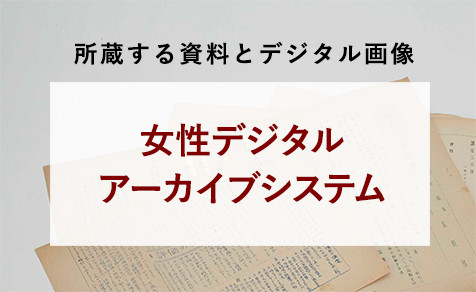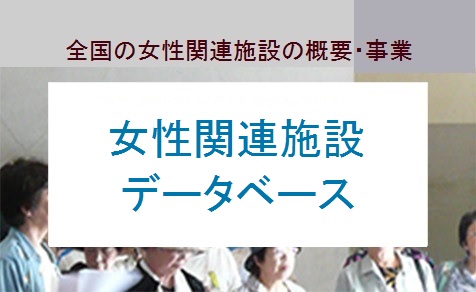国際連携
- (NWEC・ヌエック)男女共同参画の推進機関
- 国際連携
- NWECグローバルセミナー
- 2019年度 NWECグローバルセミナー ジェンダーとメディア
NWECグローバルセミナー
- 実施報告
-
2019年度 NWECグローバルセミナー ジェンダーとメディア
開催期間:2019年12月6日(金)
開催場所:一般財団法人主婦会館 プラザエフ地下2階 クラルテ /
国立女性教育会館では、アメリカから専門家を招聘し「ジェンダーとメディア」というテーマで、NWECグローバルセミナーを次の内容で開催します。
国立女性教育会館は、令和元年12月6日(金)に、「ジェンダーとメディア」をテーマとした2019年度NWECグローバルセミナーを、主婦会館プラザエフ(東京都千代田区)において開催し、内外から約100名の参加者があり、活発な議論が行われました。
第I部基調講演
 第I部基調講演
第I部基調講演
第Ⅰ部基調講演は、ジーナ・デイビスメディアにおけるジェンダー研究所(本部 ロサンゼルス)所長のマデリン・ディ・ノーノ氏による「メディアにおけるインターセクショナリティ(交差性)を問い直す」と題する、詳細な活動報告です。
ジーナ・デイビスメディアにおけるジェンダー研究所は、俳優のジーナ・デイビス氏が2004年に設立したメディア・エンターテインメント業界で唯一、実証的な調査研究に基づいて活動する非営利団体です。
 マデリン・ディ・ノーノ氏
マデリン・ディ・ノーノ氏
基調講演の冒頭では、メディアは私たちの価値観に大きな影響を及ぼしており、例えば、人口の51%を女性が占めるにもかかわらず登場人物の男女比は2:1で、エンターテイメント、メディアで女性の人物が登場する機会が奪われていることを指摘します。1日7時間以上メディアに没頭する子どもたちのメディア消費が心の健康に影響を与え、思春期の鬱が52%増加している現状、そしてメディアで女性が性的対象として描かれることによって少女の摂食障害、自尊心の低下、鬱病につながること等が紹介されました。
こうした現状を改善するためには、スクリーン上での描写を修正することによりプラスの影響をもたらすことができると述べ、登場人物のジェンダー格差、リーダーとしての女性の描き方、人種・障がいの描き方などについて詳しい調査の結果を示します。また興行成績のデータからは、女性が主役を務める映画が高い興行成績を収めており、白人/有色人種がダブル主演を務める家族向け映画の興行成績がもっとも高く、白人が主演を務める映画の平均78億円に対し、ダブル主演映画は平均約254億円であるとの結果から、メディアやエンターテインメント分野にジェンダーと多様性の視点を導入することが現状を打開する道につながると、示唆していきます。そのための具体的な方法は、概要、脚本、配役に具体的な情報を加える、男性の登場人物の名前を女性の名前に置き換える、人種を盛り込む、性的指向を盛り込む、障がいを盛り込む、などです。
女性は主体性を持った人物として描かれているか? 過度な性的対象になっていないか? ユーモアのセンスはあるか?などと問いかけ、多様なバックグランドを持つ作家・監督の採用、公平なマーケティング資源の分配、幅広い層の人々の経験を反映するストーリー、脇役の多様化などの具体的な提言で締めくくりました。
第II部パネルディスカッション
 第II部パネルディスカッション
第II部パネルディスカッション
第Ⅱ部のパネルディスカッションは、第Ⅰ部の発表を受けて、「メディアを通じた女性のエンパワーメント」をテーマとした、3つの報告と議論です。
田中東子氏(大妻女子大学文学部コミュニケーション文化学科教授)による「日本のメディアに〈交差性〉はあるのか?」はまず、キーワードとしての交差性の概念の定義からはじまりました。1990年代以降、「ポストフェミニズム」という状況が到来し、第二波フェミニズムの成果を受け止め、その限界を批判する新しい世代の女性たちが「交差」という概念を重視し、フェミニズムの新たな潮流を紡いでいます。第二波フェミニズムの白人中心主義的・中産階級的な様相を批判してきたブラック・フェミニストと有色人種のフェミニストたちは、性差別の問題、レイシズム、経済的格差などへの取り組みを通じ、交差的なアプローチへと至る視点を切り開いたのです。人種や階級、セクシュアリティや年齢、さまざまな障がいなど、多様なアイデンティティとの交錯を通じて権力関係を分析することの重要性を強調する言葉で、キンバー・ウィリアムズ・クレンショーによって導入された、と言います。
 田中東子氏
田中東子氏
本日の基調講演は、このような「交差性」という概念の下で展開され、実証データとして検証したものです。日本の状況を振り返ると、メディアにおける「ジェンダーと交差性」というテーマへの取り組みは20年以上遅れているとのこと。日本のメディアにはなぜジェンダー視点がないのかについて、田中氏は、①メディア産業での従事者のジェンダー構成の問題、「交差性」以前に「ジェンダー平等」も達成されていないメディア文化にはどのような弊害が生じるのか、②メディア制作者によるコンテンツとそれを受け取る女性たちの間に生じた乖離がSNSを通じて顕在化、③2015~2019年までに自治体や企業の広告での女性の表象について、多くの女性たちから批判の声があがっている、の3点をあげています。
その結果、固定的性別役割分業を強調したり女性の商品化を想起させる広告や、アダルトビデオの手法を盛り込んだ動画やポスターの公開が相次ぎ、次々と炎上しては取り下げられるものの、また新しいものが登場するという事態が繰り返されています。民間企業だけでなく、自治体や大学など公共性の高い組織もこのようなPR動画を制作してしまうという事態に陥っていると指摘します。
これからの新しい方向としては、「#metoo」運動を受けて、「#kutoo」の広がりや職場において女性のみパンプス着用が強制されることに対する抗議行動が始まっており、こうした行動が今後、広範に展開されていくだろうという予測で締めくくられました。
つづいての根本かおる氏(国連広報センター所長)による「国連のコミュニケーションとジェンダー平等」は、国連広報センターの紹介から始まりました。同センターは、ニューヨークの国連本部直属の事務所で、1958年の開設以来、日本と国連の架け橋のような存在だということです。
 根本かおる氏
根本かおる氏
国連では「国連持続可能な開発サミット」(2015年にニューヨークの国連本部で開催)の成果文書として採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」の行動計画としてかかげた「持続可能な開発目標(以下、SDGs)」を推進しています。17の目標と169のターゲットからなるSDGsは経済成長、社会的包摂、環境保護からなる3つの側面を統合的に推進することをめざしており、一連の目標を達成するためには、分野横断的課題のひとつであるジェンダー平等の推進は重要な要素であると強調します。
SDGsの採択から4年が経過しましたが、第5目標ジェンダー平等の進捗状況を検証すると、政治分野における女性の参画では一定の進展がみられた反面、女性に対する暴力や、児童婚等の課題が山積しています。社会に根強く残るジェンダーに係る無意識の偏見を取り除くためには、幼少期からの教育が鍵となります。根本さんの報告では、未就学児へのアウトリーチの一環として、子どもたちに人気の高い機関車トーマスに女性のキャラクターを設定して、平易な言葉でSDGsやジェンダー平等を学ぶことができる動画が紹介されました。
最後の報告は、青木玲子氏(国立女性教育会館情報課客員研究員)による「メディアを通じた女たちのエンパワーメント」です。
 青木玲子氏
青木玲子氏
近年、阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」など多くの災害関連の記念館や記念碑、メモリアルホールが建てられています。しかし、語り部プロジェクトや体験コーナーなどに女性たちの記録は、残されているだろうか、と問いを発し、災害後の女性たちの活発な動きを追います。東日本大震災を契機として発足した「フォトボイス・プロジェクト」は、被災した女性たちが、写真と「声(メッセージ)」を通して、地域主体の復興をめざして多様な視点から被災経験を記録・発信する活動をサポートしています。展示会やインターネットなどを通して社会に発信し、写真を持ち寄り、グループで話し合いを重ねるなかで、自分や周りの人の視点、地域社会や社会全体の課題などをより深く理解しようとしているのです。また、被災女性の声をすくい上げるもうひとつの取組みとして、イコールネット仙台が実施した講座「ししゅうで伝える『わたしの物語』-東日本大震災の記憶-」についても紹介されました。
女性の災害記録活動は、災害を経験した女性たちのエンパワーメント支援の意義を持つことから、声をあげにくい人々が地域や社会のさまざまな問題・課題を掘り起こし、共有し、エンパワーメントして解決に向け発信していくことが急務だと提言されています。
持続可能なメディアシステムに向けては、以下の6点を強調して、報告の結論とされました。
1 被災者の体験の重要性
2 多様な人々への配慮
3 復興・防災政策に向けてのジェンダー視点の重要性
4 災害プロセスの顕在化
5 平時からの男女共同参画の推進が防災・復興の基盤
6 マスメディア、ジェンダー視点を持った活動グループとの連携
「交差性」という新しい概念を、多角的にとらえようとする熱気あふれる議論が展開されたセミナーとなりました。
当日配布資料
国際連携
- NWECの国際連携事業について
- 国際研修
- 2019年度アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成30年度アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成29年度 アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成28年度 アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成27年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成26年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成25年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成24年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成23年度 アジア太平洋地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー
- 平成22年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー
- 平成21年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー
- 平成20年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー
- 平成19年度 アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー
- NWECグローバルセミナー
- 令和7年度NWECグローバルセミナー テクノロジーを悪用したジェンダーに基づく暴力(TFGBV)への対応 ~見えない危害を根絶するためのアプローチ~
- 令和6年度NWECグローバルセミナー ジェンダー平等とケア
- 令和5年度NWECグローバルセミナー 誰一人取り残さないジェンダー主流化に向けたメカニズム
- 令和4年度NWECグローバルセミナー デジタル技術はジェンダー平等を推進するか?
- 令和3年度 NWECグローバルセミナー ジェンダーに基づく暴力との闘い ーコロナ危機からの”より良い復興”に向けて
- 令和2年度 NWECグローバルセミナー 新型肺炎とジェンダー
- 2019年度 NWECグローバルセミナー ジェンダーとメディア
- 平成30年度 NWECグローバルセミナー 女性の活躍促進に向けた取組み アイスランドの経験から学ぶ
- 平成29年度 NWECグローバルセミナー 女性の活躍促進に向けた取組み ドイツの経験から考える
- 平成28年度 NWECグローバルセミナー 女性の活躍促進に向けた取組み~ヨーロッパの経験から考える~
- 平成27年度 NWEC国際シンポジウム ジェンダー平等と女性の経済的エンパワーメント
- 平成26年度 NWEC国際シンポジウム~ダイバーシティ推進と女性のリーダーシップ
- 平成25年度 NWEC国際シンポジウム 男性にとっての男女共同参画
- 平成24年度 NWEC国際シンポジウム 女性に対する暴力のない社会の構築に向けて
- 平成23年度 NWEC国際シンポジウム 災害復興とジェンダー
- 平成22年度 女性のエンパワーメント国際フォーラム 女性リーダーの育成に果たす教育の役割
- 平成21年度 女性のエンパワーメント国際フォーラム 女性に対する暴力の撲滅に向けて
- 平成20年度 女性のエンパワーメント国際フォーラム〜人身取引問題の解決に向けたグローバル・パートナーシップ〜
- 30周年記念国際シンポジウム
- 国際協力機構との連携
- 令和7年度課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」
- 令和7年度課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」
- 令和7年度バングラデシュ国別研修「ジェンダーに基づく暴力撤廃に向けた能力強化」
- 令和6年度課題別研修「人身取引対策グローバル協力促進」
- 令和6年度課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」
- 令和5年度課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 令和5年度課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」
- 令和4年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 令和4年度 課題別研修「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」
- 令和3年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 令和2年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 2019年度課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 平成30年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 平成29年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 平成28年度 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」
- 中米・カリブ地域における女性の経済的自立に関する基礎情報収集調査ワークショップセミナー (エルサルバドル・ドミニカ共和国)
- 平成27年度 JICA課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進セミナー」
- 中南米地域広域ジェンダーセミナー
- 平成26年度 JICA課題別研修「アジア諸国における人身取引対策協力促進セミナー」
- 平成25年度 JICA地域別研修「アジア諸国における人身取引対策協力促進セミナー」
- 平成25年度 JICA「カンボジア ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ2 2013年度国別研修」研修生一行が来館
- 平成24年度 JICA地域別研修「アジア諸国における人身取引対策協力促進セミナー」
- 平成23年度 JICA国別研修タイ「人身取引被害者支援に関する日タイ合同ワークショップ」
- 平成22年度 女性の教育推進セミナーⅡ
- 平成22年度 JICA国別研修タイ「人身取引に関する日タイ合同ワークショップ」
- 平成21年度 女性の教育推進セミナーⅡ
- 平成21年度 JICA国別研修タイ「人身取引に関する日タイ合同ワークショップ」
- 平成21年度 国別研修ナイジェリア
- 平成20年度 女性の教育推進セミナーⅡ
- 平成19年度 国別研修(カンボジア)
- 平成18年度 女性の教育推進セミナーⅡ
- 平成18年度 国別研修(アフガニスタン)
- 国際会議・国際交流
- 韓国女性政策研究院主催「アジア太平洋開発ジェンダーフォーラム」、韓国両性平等教育振興院、ソウル家族プラザ・女性プラザ訪問
- フィリピン大学ヴィサヤ校 Hilado教授来館
- 「第44回嵐山祭り」に出展します
- 「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)に出展しました(報告)
- 「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)に出展します
- 清泉インターナショナルスクールの小学生とオンライン会議
- マンスフィールド・フェロー来館
- 第69回 国連女性の地位委員会報告
- JICA課題別研修「中米統合機構加盟国向け ビジネスを通じた女性のエンパワメント」研修員来館
- サスティエ・ムブンバ・ナミビア共和国大統領夫人来館
- べアテ・シロタ・ゴードンアーカイブ資料受贈記念研究会開催
- 第68回 国連女性の地位委員会報告
- 韓国女性政策研究院(KWDI)との懇談会
- フィンランド女性協会連合(NYTKIS)事務局長カッコラ氏の上川外務大臣表敬訪問
- フィンランド女性協会連合(NYTKIS)事務局長カッコラ氏の来日プログラム
- 第67回 国連女性の地位委員会報告
- 韓国女性政策研究院(KWDI)とのウェビナー開催報告(オンライン)
- 第66回 国連女性の地位委員会(ハイブリッド開催)報告
- 筑波大学「Appropriate Technology(適正技術教育)」プログラム大学院留学生への情報提供(オンライン開催)
- 第65回 国連女性の地位委員会(オンライン開催)報告
- 第65回 国連女性の地位委員会(オンライン開催)
- 講演会「ミルズカレッジのベアテ・シロタ・ゴードンアーカイブ」
- 2nd Asian Gender Trainers’ Network Program 参加報告
- 第64回 国連女性の地位委員会
- 国立台湾大学 Wang教授来館
- 【NPO法人日本女性技術者科学者ネットワーク 男女共同参画学協会連絡会】第9回日中韓女性科学技術指導者フォーラム
- 韓国女性政策研究院(KWDI)研究員来館
- ベトナム国防省来館
- 先進7カ国の女性リーダーに関する世論調査「レイキャビク・リーダーシップ指数」報告会
- 広西チワン族自治区婦女連合会代表団 来館
- 第63回 国連女性の地位委員会参加報告
- 韓国両性平等教育振興院2018年度国際シンポジウム「学校におけるジェンダー平等教育」
- 中華全国婦女連合会 来館
- 第7回ジェンダー統計グローバルフォーラム
- 第62回国連女性の地位委員会参加報告
- UN Women石川雅恵所長来館
- 蔚山(ウルサン)施設公団 女性人力開発センター来館
- ドイツにおけるジェンダー平等
- 韓国両性平等教育振興院「女性のリーダーシップをエンパワーする:影響とイノベーションの拡大」
- 第61回 国連女性の地位委員会出席
- バティス女性センター(Batis Center for Women)来館
- 国際会議「持続的開発のためのジェンダーに配慮した教育」
- 第60回 国連婦人の地位委員会出席
- 「第7回アジア太平洋地域における開発とジェンダーフォーラム」が開催されました
- 平成27年度 職員研修(男女共同参画)
- ベトナム女性連合の女性開発センター視察団来館
- ベトナム国防省代表団来館
- 第59回 国連婦人の地位委員会
- フランス女性研究者来館
- カンボジア王国で学術調査を実施
- 韓国女性政策研究院(KWDI)前女性親和政策戦略委員長ヤン・エギョン氏来館
- 中華人民共和国で学術調査を実施
- 第58回 国連婦人の地位委員会出席
- お茶の水女子大学/カナダ女性研究者来館
- カンボジア王国で予備調査を実施
- フィリピン共和国で学術調査を実施
- カンボジア王国法務省次官が来館
- 韓国両性平等教育振興院(KIGEPE)等訪問
- 第57回 国連女性の地位委員会出席
- インドから災害管理専門家が来館
- 韓国女性政策研究院(KWDI)副院長一行来館
- 平成25年度 JICA「カンボジア ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ2 2013年度国別研修」研修生一行が来館
- ストラスブール大学 シュスター博士来館
- 第5回 人の移住に関する世界社会フォーラム
- 韓国女性政策研究院(KWDI)訪問
- カンボジア王国女性省関係者来館
- ベトナム財務省・女性の地位向上委員会代表団来館
- ハワイ大学表敬訪問
- 米国・日本・韓国・フィリピンの女性リーダーの学際的知的交流プログラム
- ハワイ東西センター バーカー博士来館
- 第56回 国連女性の地位委員会出席
- ベトナム情報通信省職員来館
- 韓国両性平等教育振興院来館
- 2011 Asia Women Eco-Science Forum(日中韓科学技術指導者フォーラム)
- カンボジア王国女性省大臣来日
- 女性研究者のエンパワーメントと新領域創成に向けた日米シンポジウム
- カンボジア王国女性省と交流と協力に関する協定を締結
- カンボジア王国女性省主催国際会議
- 中国延辺大学女性研究センターと交流・協力協定を締結
- フィリピン大学機構と学術協力に関する協定を締結
- 韓国女性政策研究院(KWDI)25周年記念式典に出席
- 国立女性教育会館30周年記念国際シンポジウムを実施
- 国立女性教育会館・韓国両性平等教育振興院協定締結記念シンポジウム
- 韓国両性平等教育振興院の国際シンポジウムに出席
- 韓国女性開発院と研究交流・協力協定を締結
- 韓国両性平等教育振興院と交流・協力協定を締結
- (NWEC・ヌエック)男女共同参画の推進機関
- 国際連携
- NWECグローバルセミナー
- 2019年度 NWECグローバルセミナー ジェンダーとメディア